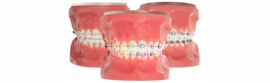細々と続けてきたこのコラムですが、今回で100回目の投稿となりました。平成23年にスタートして、足掛け14年かかりましたが、皆様のおかげで何とか続けてくることができました。心より感謝申し上げます。今回はいつもと趣向を変えて、私の父親でもある前院長に言われて今も肝に銘じている言葉についてお話したいと思います。
細々と続けてきたこのコラムですが、今回で100回目の投稿となりました。平成23年にスタートして、足掛け14年かかりましたが、皆様のおかげで何とか続けてくることができました。心より感謝申し上げます。今回はいつもと趣向を変えて、私の父親でもある前院長に言われて今も肝に銘じている言葉についてお話したいと思います。
私は平成16年に大阪大学大学院を修了したのち、大阪大学歯学部付属病院に勤務し、平成17年より大西矯正歯科クリニックの副院長に就任しました。今からちょうど20年前になります。その時は父親が院長としてバリバリ働いていました。大学にいた頃は、先輩の先生に色々教えてもらい、矯正治療の基礎を学ぶことができましたが、父親の治療を見て、それまで自分がやっていた治療との違いにとても驚きました。予知性の高い診断、堅実な治療手順、治療後の高い安定性など、それまで大学病院で学んだこととはレベルの異なるクオリティの高い治療に感心し、尊敬いたしました。前院長の考え方や治療法を一から学び直そうと思い、治療方針や治療手順を日々学び、吸収する毎日であったことを覚えています。
副院長に就任して初めの頃は、治療法などについてよく前院長に質問や相談をしていたのですが、その際に言われた言葉があります。「ヒーローになろうとするな。臨床医は普通の症例を普通に治せたらそれでいいんや。」これを言われた時、ある種、頭を叩かれたような衝撃がありました。大学病院にいた頃はどちらかというと、あまり他の人がやらないようなやり方、ダイナミックで他の先生が驚くような治療法、セオリーから外れた奇抜な方法などがもてはやされていたような気がします。おそらく前院長は、そのような考え方は危険で、臨床医には必要ないことだと暗に諭してくれたのだと思います。
「当院では歯を抜かずに治療できます」とか「外科手術しなくても治せます」「就寝時だけの装置の装着で治療可能です」等、ネット上には自分の技術や装置がいかに優れているかをアピールする文言にあふれています。多くの先生が考える妥当な方法やセオリーから逸脱した治療法を選択しても、それでうまく治ることも確かにあるのですがそれは稀で、その裏でうまく行かない症例も沢山生まれてしまうのが通常です。すべてうまくいくのであれば、それが妥当な標準的な治療法ということになるはずです。たまたま治療が上手くいった患者さんにとっては、その先生は素晴らしい先生ということになるのですが、現実は果たしてそうなのでしょうか?
ここで問題になるのは、「インフォームドコンセント」という概念です。日本語では「説明と同意」と訳されることが多いです。すなわち医師や歯科医師が患者さんに対して、病状や治療法を十分に説明し、患者さんがそれを理解・納得した上で、治療を受けることに同意することです。元々は、説明などをあまりせず、治療をどんどん進める先生が多く、患者さんの不信感を招いたりトラブルが多く起こったため、患者さんが理解できるようにしっかりと説明して、納得と同意をしていただい上で、治療を進めるようにしましょうという今では当たり前になっている考え方です。治療法の決定の主体はドクターではなく、あくまで患者さんにあるということです。しかし、患者さんの同意を得ているという理由で、うまく治らない可能性が高い治療法を平気で行う先生がいるのも事実です。私はこれはとてもおかしいことだと思っています。
「うまく治らない可能性が高い治療法を患者さんが希望しているから」とか、「患者さんの同意を得ているから治療結果がどうなっても責任はない」とインフォームドコンセントをまるで免罪符のようにとらえて無理な治療をし、その結果やはりうまくいかず、患者さんが治っていないと訴えても「初めからその可能性があることは説明していたでしょ?」「その治療法をすることに同意したでしょ?」と先生に言われ、見放されてしまうということが起こってしまいます。時間と費用をかけてうまく治らず、結果誰も幸せにならないという不幸な事態になってしまいます。こういうことは臨床医の本来の仕事ではないはずです。
当院の治療法は、「抜歯すべき症例は抜歯する」「外科手術が必要な患者さんは手術する」「インビザラインで治療困難な場合はワイヤーで治療する」等、ある意味普通で基本に忠実な治療法を選択することが多いです。治療結果への確証がない限り、セオリーから外れた突飛な治療法はしないように心がけています。「普通のことを普通にする」ということは、一見当たり前で簡単そうですが、実はとても難しいことです。当院では手堅いオーソドックスな治療法を行うことが多いですが、最終的にはそれが患者さんにとって無理のない良い治療結果をもたらすと信じています。
臨床医はヒーローではありません。真のヒーローは費用も時間もかかり、面倒な装置を頑張って着けていただいている患者さんです。臨床医は自分がどれだけすごいんだとかアピールするのではなく、ただ粛々と患者さんを治療のゴールに導いていけばそれでいいんだと前院長は伝えたかったのだと思います。若き日に前院長に言われた言葉を胸に、今も日々の診療に当たっています。
2025月08月16日
院長 大西 秀威